「突然街中に出現する本屋・
いつの間にか、日常に「本」が忍び込んでくる……。

©anne imai
昨冬、「街に染み出す本たち〜books seep into the town〜」と題したブックイベントを、友人・小林空とともに開催した。
品川区にある中延商店街のフリースペースに、1日限定の“ゲリラ本屋”を開く試みである。
もし八百屋に、野菜に紛れて本が並べてあったら、きっと手を取らずにはいられないのでは?
僕らは棚に芝を敷き、野菜を飾り、「八百屋」を作った。
劃桜堂はこのような活動を通じて、本に出会うきっかけづくりをしている本屋である。
「イマドキの若者は本を読まん。けしからん!」と巷で叫ばれているが、そうではない。「本が読まれないのではない。本と出会うきっかけがないだけだ」と、文字どおり叫びたい。
だが、しかし。「八百屋の本屋」では目論見が外れ、本はとんと売れなかった。
代わりに、店頭の飾りに置いた将棋盤に、子どもとOLの女性が食いついた。
八百屋に将棋が置いてあれば、将棋をする人はいる。 ……というわけで、今回は「八百屋でよく売れる本」を紹介する。
路
吉田修一(著)、文藝春秋、2015年
誤解を怖れずに言えば、八百屋に行く目的の80%はカレーの材料を買うことにある。
そしてカレーを作る人の70%は、「日常に刺激が足りないのは、スパイスが足りないからだ」と思っている。
『路(ルゥ)』は台湾に新幹線を走らせた人達の物語である。「路」を中国語で発音すると「ルゥ」なのである。
商社の台湾支局で勤務する春香と、日本で働く台湾人の建築家・人豪。2人は学生時代に台湾で出会い、互いに惹かれ合うが、長い間再会を果たすことはできなかった。
そんな2人が台湾新幹線事業を通じて再び再会する。台湾に生まれ戦後日本に引き揚げた老人や、台湾人の青年、それぞれが置き去りにされた思い出を迎えに行く。
日本、台湾の過去と現在を通じて、明日に続く「路」を描いていく刺激的な作品である。
さようなら、オレンジ
岩城けい(著)、筑摩書房、2015年
風邪の引き始め、少し身体がだるくてビタミンを補給しようと思う。
重い足取りで八百屋へ向かう。そこで新鮮な野菜たちが目に飛び込んでくる。
「ああ、今日は鍋にしよう」
ネギと白菜、椎茸に人参を買う。
少し上機嫌の帰り道、ふと思い出す。
「オレンジ、買い忘れた」
……さようなら、オレンジ。
本書はこのような内容と全く関係がない。
舞台はオーストラリア。アフリカからの難民・サリマと、自分の夢を諦め夫について渡豪した日本人女性「ハリネズミ」の物語。
あたりまえに平和があって、あたりまえに言葉が通じて、あたりまえに八百屋がある日常とは違い、戦火を逃れた難民女性が、言葉の通じない異国で、苦労しながらも精肉店で働く「日常」を描いている。
ホームレス農園 ――命をつなぐ「農」を作る! 若き女性起業家の挑戦
小島希世子(著)、河出書房新社、2014年
八百屋の店頭に並ぶのは、みずみずしく輝く野菜だけではない。野菜を作る人たちのアツイ気持ちも、お店にはあふれている。
人一倍農業に情熱を注ぐ女性起業家が、「仕事はあるけど働き手がいない」農家と、「働く意思はあるけど働く場所がない」ホームレスをつなぐ。
身近にある野菜を通じて、社会を変えることができる。人々に生きがいを与えることができる ーーホームレスというと、なんだか「関わりを持ってはいけない」と思う人もいるだろう。
ホームレスの人々に対する距離感。すなわち彼らに理解を向けようとしないのは私たちの問題で、理解しだいで変えられることもできるのではないだろうか。
本書では彼らの人間味あふれる素敵な一面を垣間見ることができる。素敵な人が作る野菜は、きっとおいしい。ぜひご賞味あれ。













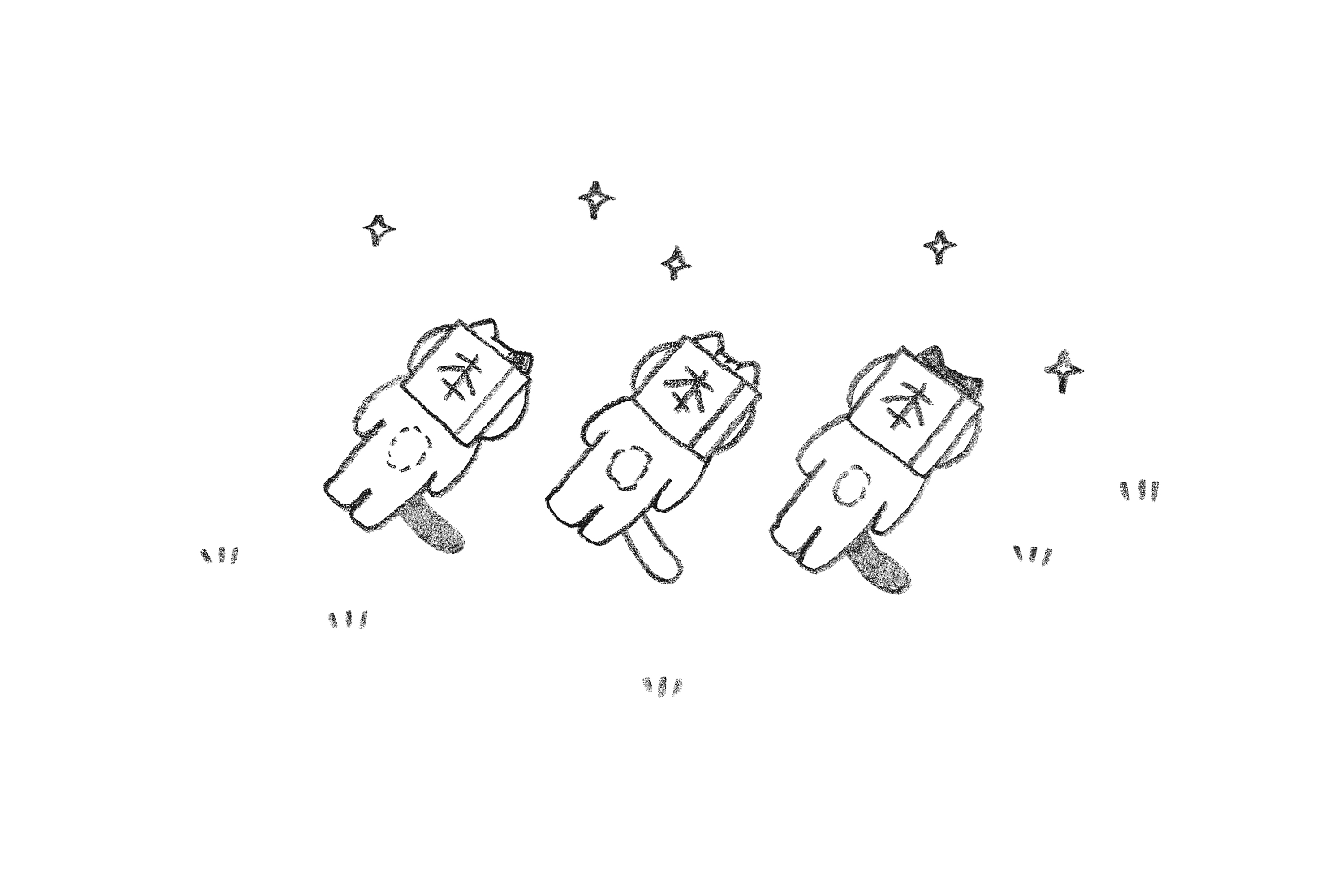
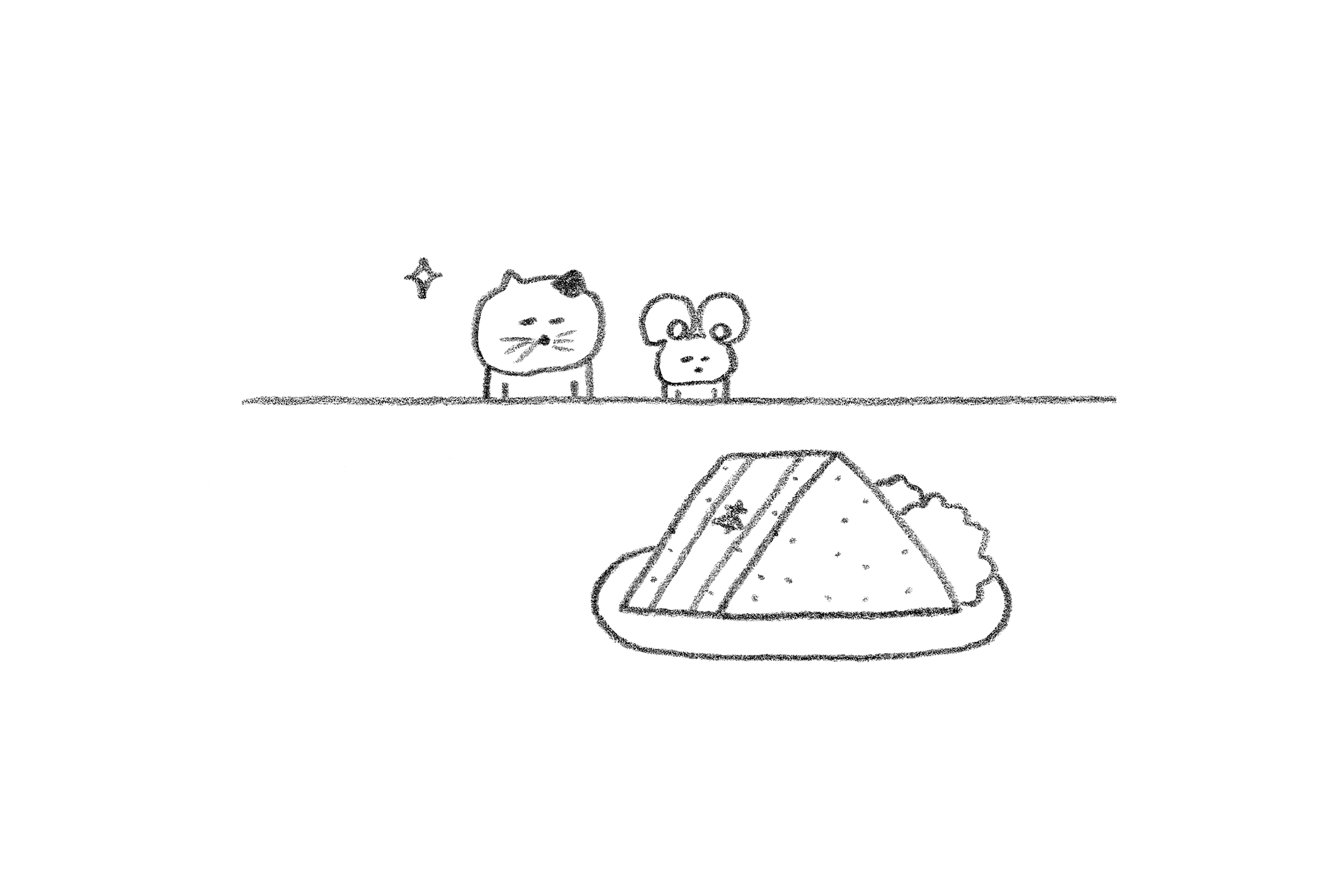
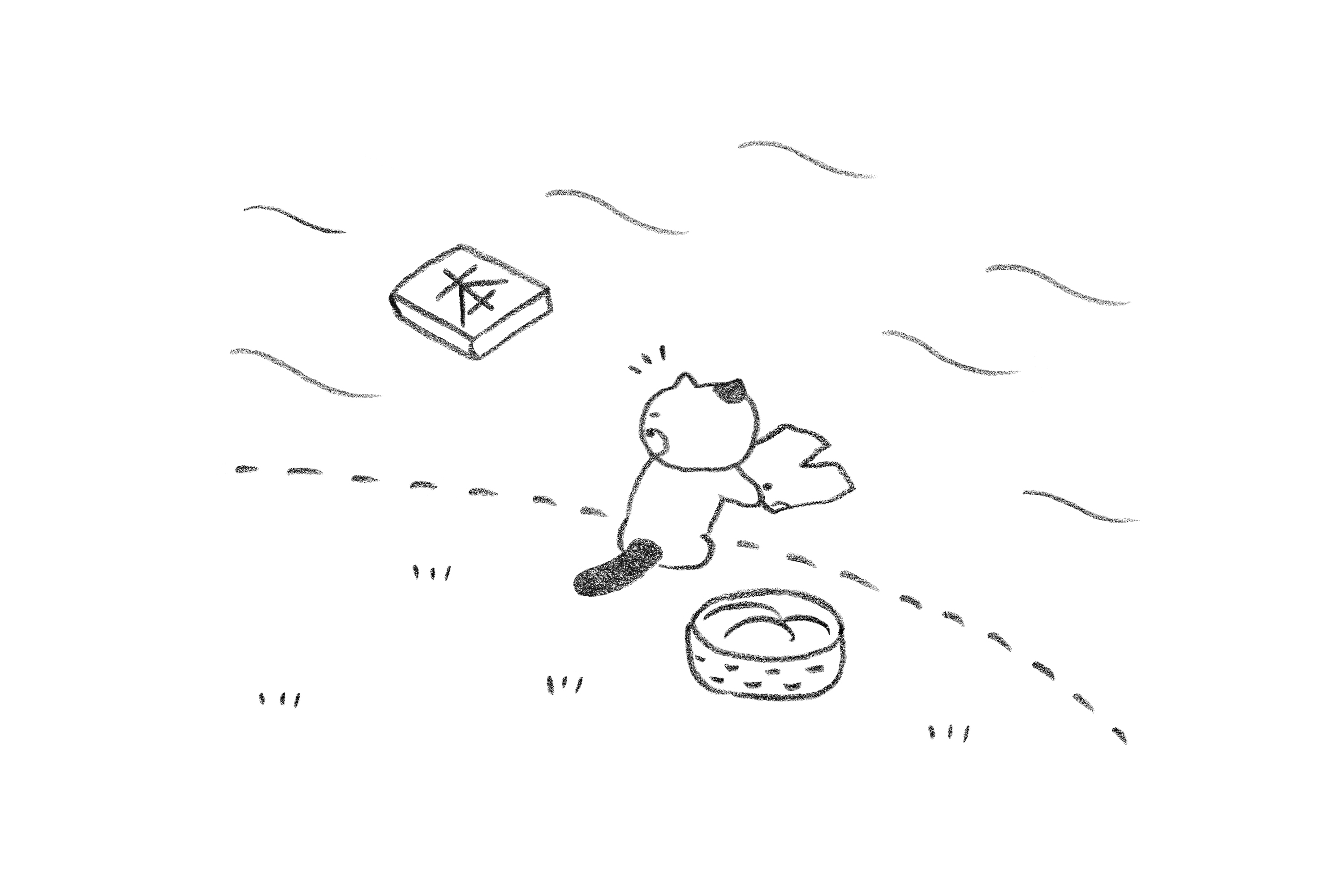
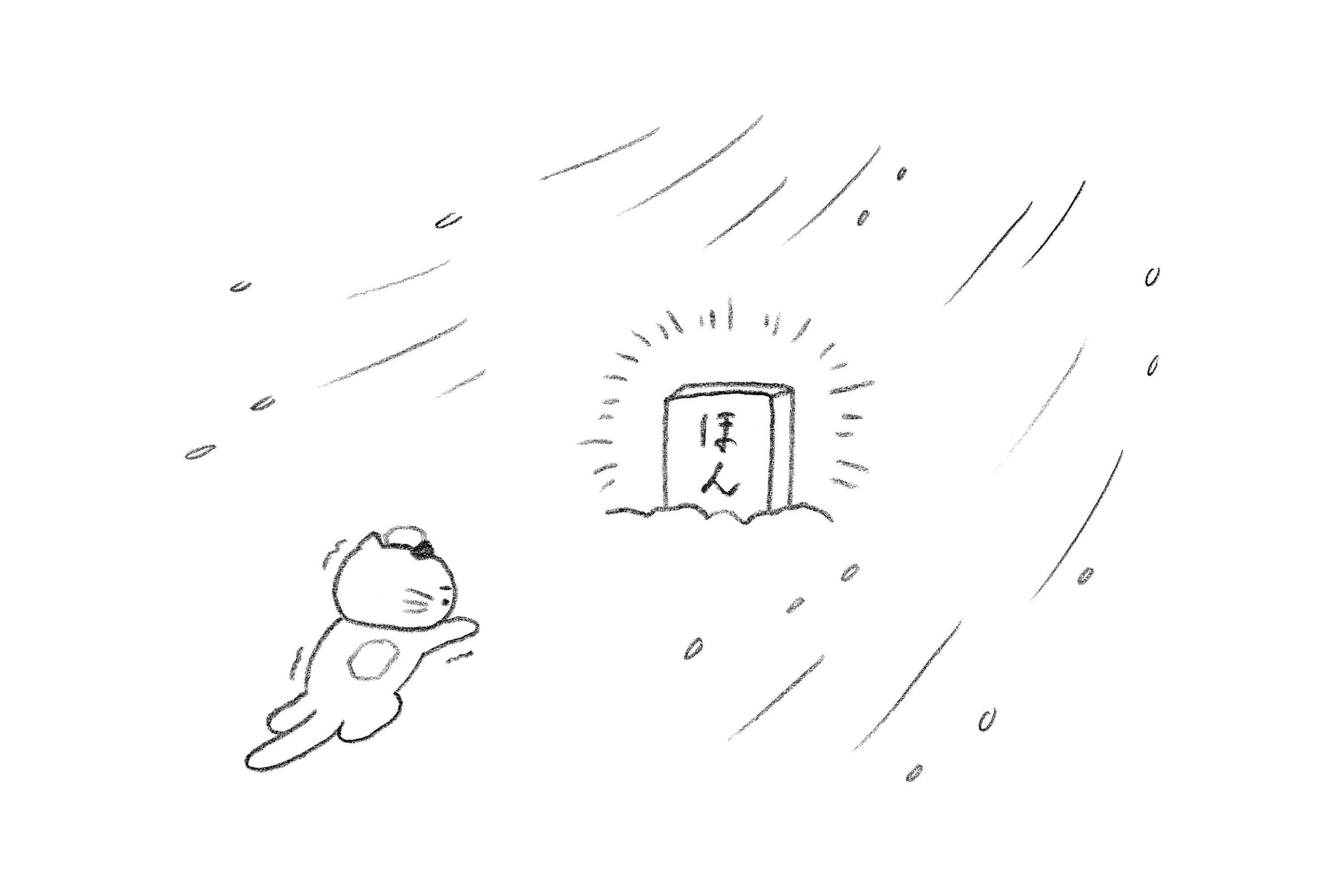

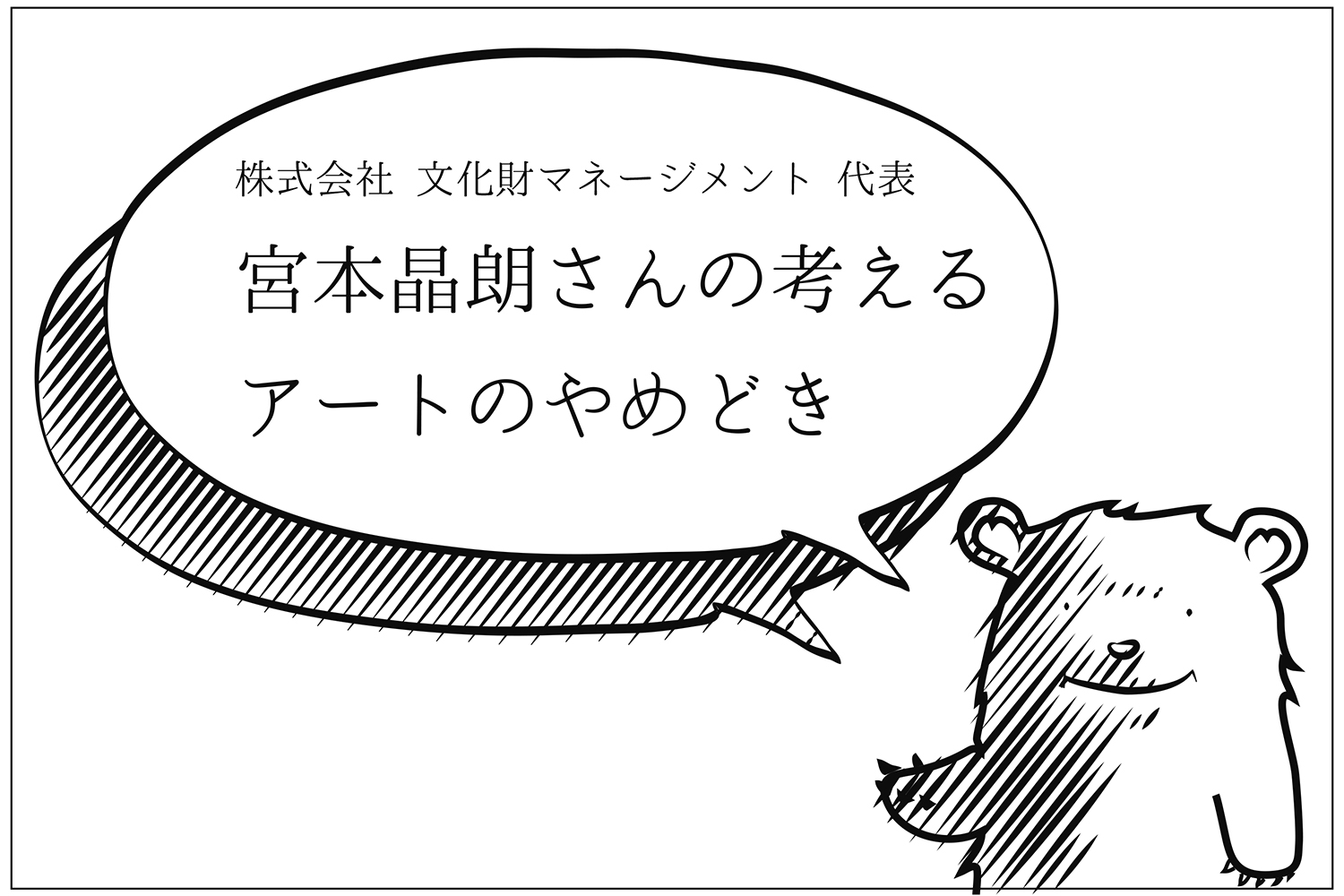

コメントを投稿するにはログインしてください。