BIOを知り、日常の中に少し取り入れてみると、身の回りのケミカルで工業的なものも、違った角度から見えて、あらためて理解できたりします。
自分自身の中に新しいモノの見方、価値観が生まれる感覚は心地良い! だから、BIOは、ラッキーなこと!
「BIO is LUCKY!」では、BIOでラッキーな情報をご紹介していきます。
2016年6月末から8日間、ドイツ・オーストリアへ視察の旅に行ってきました。その視察レポート最終回です。
一般社団法人日本ビオホテル協会の中石真由子です。
Sバーン乗車体験
ミュンヘン市内の公共交通機関には、Sバーン(都市近郊鉄道)、Uバーン(地下鉄)、トラム、バスなどがあります。
住宅展示場に向かう際に、Sバーンにも乗車しました。
乗車券にまで、国際森林認証(FSC)の紙が使用されています。

Sバーンの駅ホーム〈左〉と、乗車券〈右〉。(Photography: Mayuko Nakaishi)

住宅展示場の帰り道、緑道を歩いてたどり着いたのは、Sバーンの駅のホーム。
改札口がありませんでした。
持っていたチケットのチェックもなく、電車が入ってきて、そのまま乗り込みました。

Sバーンのある駅のホーム。(Photography: Mayuko Nakaishi)
車内では、ときどき車内改札があるとのこと。
無賃乗車の場合、60ユーロの罰金が課されるそう。
青空市場・Viktriaen Markt
「ミュンヘンの胃袋」といわれる市場・Viktriaen Markt(ヴィクトリアーエン・マーケット)。
少々お値段は高めですが、八百屋、果物屋、ハチミツ屋、菓子屋、肉屋、魚屋が集まり、おいしいものをこの青空市場で買い求めることができます。
一般の店舗に混じって、BIOのオイルやチーズ、はちみつ、紅茶のお店なども出店しています。

オリーブの種類も豊富〈左〉。BIOの紅茶の専門店も〈右〉。(Photography: Mayuko Nakaishi)

午後15時くらいだというのに、マロニエの木の下のテーブルには大勢の人たち。

(Photography: Mayuko Nakaishi)
特にサマーシーズンの時期には、ビジネスマンも朝早くから仕事を開始して、早仕舞いをし、みんなでビールを傾けながら、おしゃべりを楽しむのだそう。
そこには、短い夏を親しい人たちと存分に味わう、大人の時間の使い方があります。
ドイツにおける動物の飼い方
そういえば、ミュンヘン市内やその他地域を巡っていても、あまり犬を連れた人たちを見ませんでした。
コーディネーターの松田さんに聞いてみると……
たぶん見かけてはいるけれど、おとなしいから分かりにくいのかも。“子どもと犬はドイツ人に育てさせろ”という言葉があるとおり、躾が行き届いています。

フュッセンの街を散策。犬を連れた女性。(Photography: Mayuko Nakaishi)
ドイツには、日本のようないわゆるペットショップが存在しません。
犬の入手方法は、大きく2つ。
ブリーダーから購入するか、ティアハウスのような動物保護団体から譲渡してもらうかです。
松田さんは先日、Tierheim(ティアハイム)という「動物の家」を見学してきたそう。
Tierheimは動物保護施設で、犬以外にも、猫やハムスター、馬や豚、鳥なども収容されています。
その最大の特徴は、殺処分を行わず、年老いて認知症になっても寿命を全うさせることを基本にしているところ(ただし、厳密には、必要な場合には、安楽死の処置もあるもよう)。
希望者は、自由にティアハイムを訪れて、気になる動物を見つけることができます。
ただし、一人暮らしであったり、長時間動物が一匹だけで過ごすことになるような場合には、譲渡されないそうです。
ドイツには、動物の保護や動物の福祉に対する高い意識が長年、根づいています。
街の様子や景観
ほかにもドイツの街中で気づいたのは、どの場所も、道路や歩道、街並みがとてもシンプルで、きれいだということ。

バスの車窓から。バスから街の様子を見ることで、学ぶこともたくさんありました。(Photography: Mayuko Nakaishi)
その理由を考えてみたときに、2つのことが分かりました。
まず、自動販売機が見当たりません。
また、広告宣伝用のサイン看板も設置されていないのです。
もし日本で、自動販売機や看板のない行政特区が作られたら、人びとは、本当に必要なものを本当に必要なときに、本当に必要な方法で、手に入れる術を身につけることができるような気がします。
ドイツと隣国オーストリアの閉店法
視察レポートの第1回でもお伝えしましたが、ドイツには1900年に施行された「閉店法」があります。
時間帯が柔軟に対応されるなどありますが、小売店の営業時間は原則平日6~20時、日曜は休業です。
観光地の土産物店や一部のカフェなどは、営業時間の延長の申請をしてオープンしていたりします。

オーストリア・インスブルック旧市街の日曜日の様子。(Photography: Mayuko Nakaishi)
隣国のオーストリアも同じように規制があります。
インスブルック在住の方にお聞きしたところ、
休日は、登山やハイキング、サイクリングなどのアウトドアが中心。家族でピクニックも日常です。休日丸一日をショッピングだけで終わらせることはありません。
「Culture(カルチャー)」という言葉の語源は、ラテン語の「Colere」。
「土地を耕す」「心を耕す」という意味に由来して、いまの「教養」「文化」に派生しました。
国や風土が違っていても、教養や文化を高めることは共通です。
カルチャーには、世の中を変える力があります。
BIOは、そのきっかけの一つ。
私たち自身で、持続可能なサスティナブルな社会に向かって、シフトできるチャンスがあるはずです。
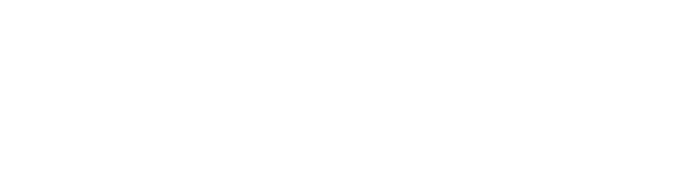














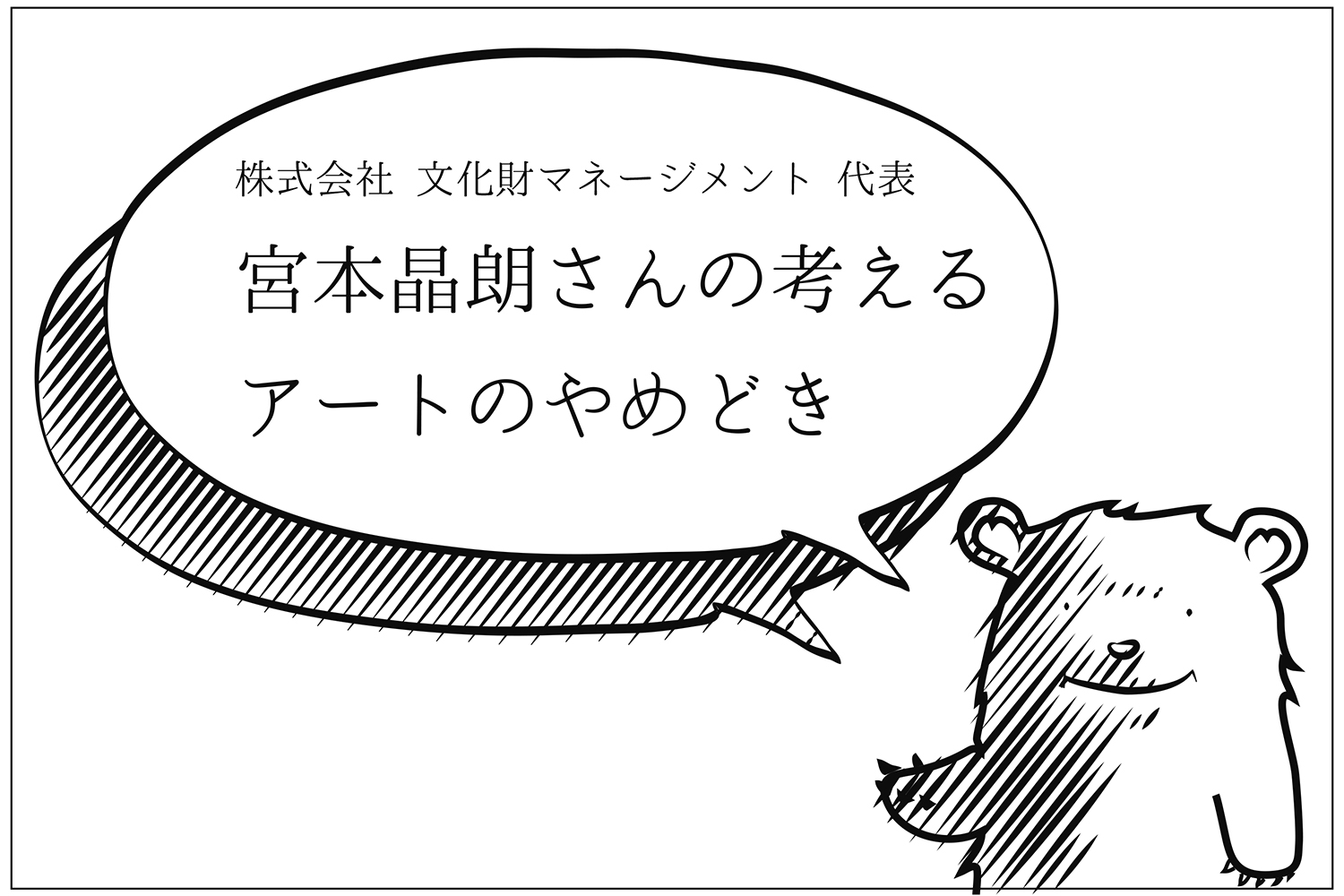

コメントを投稿するにはログインしてください。