「広告がものを売るだけでなく、社会を動かす力になったらおもしろい」。
株式会社電通でコピーライターとして活躍する傍ら、社会課題を解決する「ソーシャル・プロジェクト」を数多く手掛ける並河進さん。
手洗いを通して子どもの健康を守る「世界手洗いの日」プロジェクト(日本ユニセフ協会)、日本の女子高生と大学生が児童労働に関心を持ってもらおうと奮闘するドキュメンタリー映画「バレンタイン一揆」(NGO・ACE)、検索することで東日本大震災の支援活動に寄付を届ける「Search for 3.11 検索は応援になる」(ヤフー株式会社)。
広告が社会にできることとは? と向き合い、挑戦してきた並河進さんを紹介する。

並河進(なみかわ・すすむ)
1973年生まれ。株式会社電通 コピーライター、クリエーティブディレクター。「電通ソーシャル・デザイン・エンジン」「電通ギャルラボ」代表。東京工芸大学非常勤講師。受賞歴に、ACCシルバー、TCC新人賞、読売広告大賞など。著書に『下駄箱のラブレター』(ポプラ社)、『ハッピーバースデイ 3.11』(飛鳥新社)、『Social Design 社会をちょっとよくするプロジェクトのつくりかた』(木楽舎)、『Communication Shift 「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ』(羽鳥書店)他。
大学ではロボットを研究したいと考えていたが、希望が叶わず船舶海洋工学科(現・システム創成学科)へ。研究室に泊まり込み、船の設計システムに没頭した。研究はおもしろかったが、先輩の研究員たちの中には、家族も持たず研究所と家の往復暮らしの人も。
「自分の人生もこうなるのか」。いまの生活から飛び出し、なにか大きいことをやりたいと株式会社電通に入社した。配属は、「コピーライター」。文系の人の仕事では? と思ったが、3年間日本語の勉強をしながら企業の広告のコピーを書いた。
入社当時の1997年、日本経済は不景気に突入。企業が売りたいものを、いかに新聞広告やテレビCMで伝えるかが広告の役割だった。景気が良い時代は、商品の特長を機能的に伝えるだけではなく、世の中を元気にするようなメッセージにと、企業担当者と広告クリエイターがタッグを組んでいた。
社会に対してプラスのメッセージを広告に
会社に入り5〜6年経った頃、社会に対してプラスのメッセージを広告で伝えたいと考えるようになった。
並河さんが「カッコいい」と絶賛する、イタリアの写真家オリビエロ・トスカーニ。彼は1994年、ボスニア紛争で命を落とした兵士の服を使い、イタリアのファッションブランド「UNITED COLORS OF BENETTON」のポスター広告をつくった。これは、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)とのユーゴスラビア内戦への反戦キャンペーンだ。
ファッションブランドが、自社のきれいな服ではなく、血だらけの服を使うことは勇気を持って行動しないとできない。企業の広告をつくるとき、「表現」方法だけを変えるのではなく、社会に対してどんなことをやっていくのかという「行動」の領域に踏み込んで、いっしょに「こと」を起こすことをやりたいと思うようになりました。
しかし、最初はなかなかうまくいかなかった。
「このジュースはカロリーオフであることを伝えてほしい」と企業担当者から言われ、「ライバル社のジュースと乾杯したビジュアルで、ピース(平和)ってできないですかね?」と提案したら、「……。並河さん、疲れているんじゃないですか」(苦笑)。
社会貢献の原点
YouTubeもUstreamも普及していない2005年。並河さんはテレビ番組プロデューサーや脚本家と、インターネット動画中継番組「ブレスト」に関わっていた。
ブレストしたアイデアを実現するというこの番組の中で、ボランティアとアイドルを掛け合わせた「ボラドル」が生まれた。ボランティアには全く興味がなかったが、かけ離れたものを組み合わせたらおもしろいんじゃないか。
ファンとゴミ拾いした後にライブを行うなど試みたが、ボラドルを務めた当時15歳の鈴木りなさんに「ボランティアって誰かに言われてすることじゃない」と言われ、企画は終了。しかし、広告が社会変革を起こせたらという以前からの思いが、「社会貢献」とつながった。












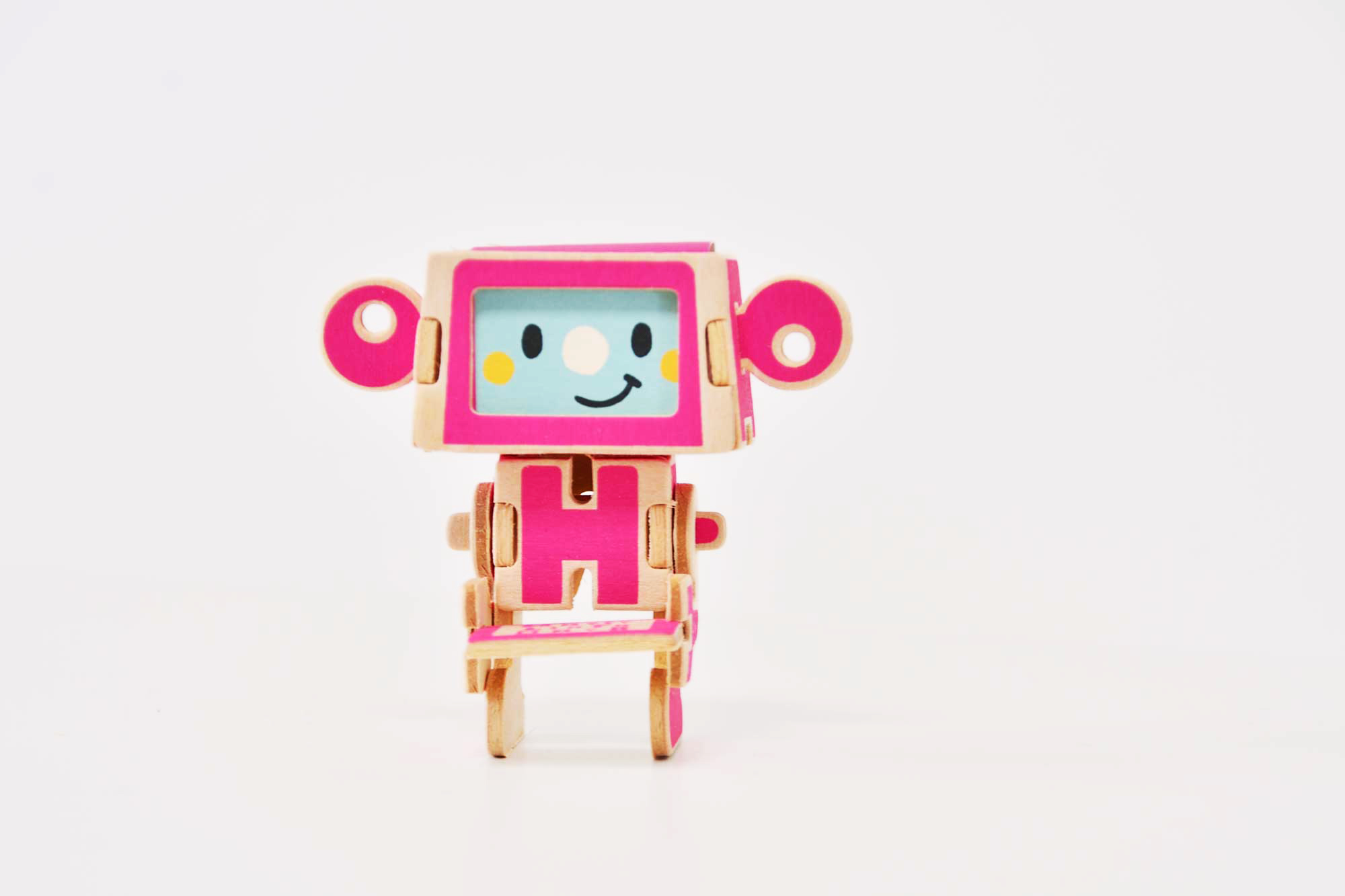





コメントを投稿するにはログインしてください。