淡くやわらかな輝きを放つ「matsurica(マツリカ)」のアクセサリー。まるで光をわたあめに包み込んだように、ふんわりと優しいその素材はガラスです。
光の表情を出すために、鏡を貼り合わせて反射を利用したり、あえて表面を曇らせて色の強さを抑えたり、見え方や変化を追求しています。
そんな「matsurica」のアクセサリーは、江戸時代末期に江戸で始まったカットグラス工法である、江戸切子の技法を基に作られています。
ガラス作家の古川莉恵さんのアトリエにおじゃまして、どんなふうに作っているのかを見せていただきました!

「matsurica」古川莉恵さん。名前は、茉莉花に由来がある。
どんなふうに作っているの?

まずは電気炉で溶かすため、ガラス板を砕く(上写真・左)。焼くと水の雫みたいになるのは、表面張力の働き(右)。

電気炉は美大入学早々、授業で作ったもの。最近故障して、当時の先生に電話して自力で直したのだとか。最大1372℃まで出ます。

むかし海や川で拾ったシーグラスのような、丸い「pebble」シリーズ。ガラスをランダムに電気炉の中に並べ、溶けて自然にでき上がったかたちを、そのまま使うのだそう。
「波や風や砂でつくられた自然のカタチ、その中に包み込まれる淡いヒカリに憧れます。」が「matsurica」のコンセプト。

鏡を間に挟み、光の反射を利用して色を映しだしたら、次は磨きへ。
研磨機は通常の江戸切子では、最後にガラスをピカピカに磨くためのもの。だけど古川さんはあえてマットに仕上げ、やわらかな光に変えていきます。

ガラスを切り込んでいく「hanabi」シリーズの場合は、半球型のガラスを使います。この原型を作るため、石膏型(上写真)にガラスの破片を詰めて焼きます。

切り込みを入れる機械も、まさに江戸切子のそれ。水を含ませたスポンジで回転刃を冷やしながら削ります。冷やしていないと熱を持ってしまい、割れてしまいます。

アトリエの中に「シュー……」と、ガラスの削れる音が響きます。力の加減を保つのに、集中力を切らしません。
これら江戸切子の技法でできるプロダクトは、ピアスなどのアクセサリーのほか、帯留めやかんざしも。
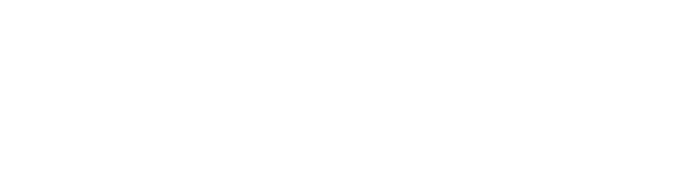






















コメントを投稿するにはログインしてください。